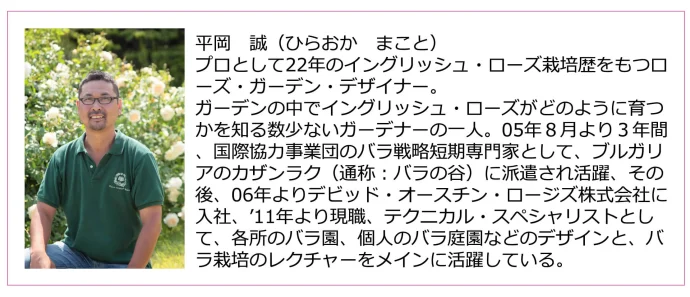イングリッシュ・ローズの生みの親 デビット・オースチン物語Ⅰ

「時代を揺れ動かすエネルギーは10年にひとつ」というフレーズをどこかできいたことがあります。確かに音楽業界や、スポーツの世界では「10年にひとりの逸材」とよく聞きますし、実際、そのジャンルでかなり突き抜けた能力、才能をもった人やグループは10年に1回のサイクルで現れていると思っていいのではないかと常々考えています。
さて、この状況を園芸界に当てはめてみると、大きなうねりともいえるような流れはその性質、つまりサイクルがどうしても1年サイクルで動かざるを得ないことを考えるとグッと間の年数は増えて、少し大げさに言えば「園芸の時代を揺れ動かすエネルギーは30~40年にひとつ」とでもいえるのではないでしょうか。

多くの皆さんがご存じのとおり、バラ育種家のデビッド・CH・オースチン氏(以下オースチン氏)が2018年の12月18日に亡くなりました。氏の育種家としての人生を振り返ってみたときに、氏の人生が全世界の園芸界においてこの30年にひとつのエネルギーと言えるほどのものであったと言っても、あまり異論を唱える人はいないのではないかと思います。それほどまでに、オースチン氏の残した足跡は大きなものであったと言えます。今回、これまでになかった側面からオースチン氏と生み出された品種が素晴らしいものだったのかということを今一度見直し、その文章をもって氏への追悼文ともさせていただければと思っています。
まず、1回目の今回は、イングリッシュ・ローズ創成期、周辺のバラをとりまく状況からとらえたイングリッシュ・ローズです。2回目は80年代90年代と世紀をまたいで海を越えた日本で起こった一大現象を、私のバラ現場での実体験から振り返ります、そして3回目はまさに本格的なインターネット時代、情報化時代ともいえる2000年代から氏の没年までを書いてみたいと思います。

歴史というものはその多くが多かれ少なかれ、いわゆる「伝え聴き」でしかありません。たとえば、父親が息子に自分が小学生の時の思い出話をするときに、あくまでそれは「父親」というフィルターを通した歴史の語りでしかないわけで、現実にその時代に人々がその時代のさまざまな状況の中で体験する事実とは、やはり乖離するもののような気がします。
バラや、園芸を取り囲む状況もこの多分に漏れず、その時代のその空気でお花や、植物を見てみないとどうしてもわからないこともあるわけです。

最初に作出したイングリッシュローズ、‘コンスタンススプリー‘(1961)
多くの方がご存じのとおり、オースチン氏が最初に世に発表した品種が1961年作出になるので、すでに70年近くの月日が流れていることになります。その間の世界のバラを取り巻く状況はほぼ180度といってもいいように変化してきたのではないかと思います。
日本の育種家と世界の育種家の作り出したその時代の代表品種を並べてみるとそれが色濃くわかります。まずは最初のイングリッシュ・ローズが作出された60年代の世界・日本を代表する園芸品種を独断で羅列してみました。
◎ハイブリット・ティーの時代を代表する品種
1960年 天津乙女(HT・黄色) 寺西菊雄
1962年 ロイヤル・ハイネス(HT・ピンク)
1963年 オクラホマ(HT・赤)
1963年 ドフトボルケ(HT・朱赤)※タンタウ ドイツ(殿堂入り1981年エルサレム大会)
1963年 パパメイアン(HT・深紅)※メイアン フランス(殿堂入り1988年シドニー大会)
1963年 パスカリ(HT・白)※ランス ベルギー(殿堂入り1991年ベルファースト大会)
1964年 ブルームーン(HT紫)タンタウ
1964年 ミスターリンカーン(HT・赤)
1965年 マリアカラス(HT・ローズピンク)
1966年 聖火(HT)日本 鈴木省三

天津乙女

ブルームーン

ミスターリンカーン

マリアカラス
見事に往年の銘花が並んでいますし、現代でも多くのファンを持つ花だと思われます。多少の私の独断はあるにしろ、これらの品種がある程度バラの世界の60年代という時代を映し出す品種群だということはおそらく誰にも異論の余地はないことだと思われます。
少し余談ですが、1963年という年はバラの世界では非常に当たり年のような気がします、というよりはバラに限らず、植物の育種の持つ特性によるもので、この年がいわゆる第二次世界大戦後の「植物あるいはバラのベビーブーム」ということができるのではないかと常々考えています。のちに世界バラ界連合によるバラの殿堂入り品種に、実にこの年の作出品種が3品種も選ばれています、2018年までで17品種しか存在しない殿堂入り品種、うち3品種が同一年作出という事実は非常に驚きを感じますが、1940年代に第二次世界大戦が終わり、各育種家がそれぞれ荒廃した自身の圃場で再度立ち上がり、再び新品種を作り出し、テストをして世に送り出す作業の結果が一気に出始めたのが60年代前半と考えると、改めてこの時代の持つエネルギーというものを感じることができるのではないかと思います。ということはオースチン氏もその当時の名だたる育種家と同じような状況を潜り抜けて、やっと最初のイングリッシュ・ローズ誕生にこぎつけたといえると考えます。

話は元にもどり、当時の全体の傾向は日本でも世界でも正にハイブリッド・ティー、大輪系一色、色目もその大きな花一輪だけで、多くの人の目をくぎ付けにするような品種が目立ちます。また、上でも書いたようにこの「花の63年組」の中でバラの殿堂入りした品種が実に3品種、更にその3品種が実際に殿堂入りした年度は1981年、1988年、1991年ということを考えると(そもそも世界バラ会連合の会議自体が70年代に始まったといわれればそれまでですが)その大輪系の世界的な影響力が非常に息の長いものであったのかがわかると思います。

パパメイアン

パスカリ
先に書いたように歴史というものはある意味その時代にあったさまざまな状況を検証して、その時代にあったと思われる仮想状況に自分を置いてみて物事を考えてみないと想像できないものでありますが、当時の状況は大輪系でなければ第一線のバラではない、と多くの人の間で考えられていたと言って間違いないのではと思われます。また、もちろん今のようにインターネットなどの情報が発達した状況でのはやりすたりの傾向と違い、ひとつの傾向が比較的長く続く傾向があったと考えられますので、人々の大輪系に対する固定観念は非常に根強いものであったのは容易に想像できます。
その中でのイングリッシュ・ローズです。オースチン氏の育種目標の中で最も重要視されていたもののひとつはもちろんオールド・ローズのもつ優雅さです。この時代の確固とした傾向とはまるで逆行するような育種の目標は、並大抵の精神力では実行に移せるものではありません。バラの育種は本当に孤独で地道な作業の連続です。しかも、その当時は育種の材料となるバラの品種を集めるのにも苦労するような時代、のちになって何回もお会いすることになるオースチン氏ですが、お会いする度に感じた眼光の鋭さはまさに、この長い苦しい時代を乗り越えてイングリッシュ・ローズを作り出しつづけることのできた、精神力の高さから来ているような気がします。

しかしながら、悪いことばかりではなく、「世界の園芸センター」ともいえるイギリスの土壌はオースチン氏をこの孤独の時代に、根底のところで支えることになります。その点ではイギリスという国の園芸文化の懐の深さをまざまざと感じることができるのですが、その「地の利」ともいえる状況の中でオースチン氏が育種を続けることができたのは、これこそイギリスという園芸王国の土壌が生み出したオールド・ローズの研究家でもある園芸家、グラハム・トーマス氏との関係が必要不可欠であったこと思われます。もちろんこのグラハム・トーマス氏の名前がのちにバラの殿堂入りを果たすオースチン氏の品種名になっていることからも、どれだけ2人がこの創成期の時代を支えあってきたかが容易に想像できます。

グラハム・トーマス
ひとことで言えば、オースチン氏のそしてイングリッシュ・ローズの序章の時代は逆境の中のひたむきな努力とイギリスならではの絆が生み出した時代だったといえるかもしれません。さて、苦悩の時代ともいえる60年代、70年代を経て時代が、世界がオースチン氏に一気に脚光を浴びせる時が訪れます。それば、次回でのお話しにさせていただこうかと思います。

チェルシー・フラワー・ショーでエリザベス女王と握手するオースチン氏