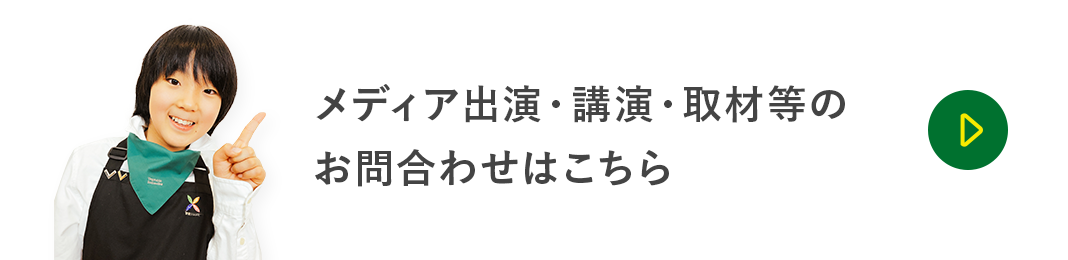目次
ニシン(鰊)を選ぶ
ニシンは鮮度落ちが早いので「エラの部分」をチェック
一般的に魚の鮮度を見る場合、まずその魚の「目」を確認します。目玉が濁らず、黒目がくっきりしている魚は鮮度が良い証拠ですが、ニシンの場合は漁獲時にすでに目の内出血しているものが多いので、鮮度の見分けにはなりません。ニシンの鮮度を確認するのは、「エラの部分」です。ニシンはエラに赤みがありますが、鮮度が落ちるとエラぶたにうっすら血がにじんだようになっています。時間が経つとその赤みが広がっていきます。エラから血水が漏れているものは避けましょう。体に張りがあり、腹がしっかりして銀色が眩しいもの、ウロコがついているものが良いです。身が厚いほど、脂が乗っていますので、刺身の場合は脂が少なくて大丈夫ですが、焼き物の場合は脂が多いニシンを選ぶとよいです。他の魚同様、鮮度が落ちたニシンは肛門が緩み、どろどろとした排泄物が漏れてきますので、肛門が締まっているものを選びましょう。水に浸かって売られているものは、その水が濁っていないかどうか確認します。
「かずのこ」はニシンの卵巣、「子持ち昆布」はニシンの卵
ニシンは別名、「春告魚(はるつげうお)」と呼ばれ、産卵時期の3~5月にかけて北海道沿岸に現れます。この時期はお刺身で食べることもでき、また卵や白子を美味しく味わうことが出来るので、生のニシンを卵ごと塩焼きにしたりします。また10~12月、産卵にそなえ夏から餌をしっかりと食べているため栄養をたっぷりと蓄えており、身に脂がのっておいしい時期でもあります。ニシンといえばすぐに思い出すのが「かずのこ」ではないでしょうか。かずのこはニシンの卵巣を塩漬けにしたもので、子孫繁栄の象徴として正月料理に欠かせません。
現在、かずのこの大半は輸入物が占めていますが、国産のかずのこは小粒で黄色が濃く美味しいといわれています。また、ニシンが卵を自然に産み付けた昆布を「子持ち昆布」と呼んでいます。ニシンは大挙して海岸に押し寄せ卵を昆布や海草等に産み付けますが、ニシンの卵は卵同士ぴったりとくっつく力が強いので、昆布にずっしりとつきます。
「ニシン」という名前の由来
身を二つに裂いて食用にすることから「二身(にしん)」となったとする説が有力です。漢字表記の「鰊」は「東の魚」という意味からです。また、「鯡」の字が当てられますが、これは江戸時代に蝦夷地の唯一の藩である松前藩が米の代わりに年貢としてニシンを徴集していました。「魚に非(あら)ず、米なり」といわれたように魚ではない扱いであったことに由来します。幼魚の頃は、イワシに姿が似ているので、東北地方では「カドイワシ」や「カド」と呼ばれることがあります。それは産卵のために押し寄せてきたニシンを門口(かどぐち)で、手づかみで獲ることからカドと呼ぶようになったとする説があります。
ニシンの卵巣が「かずのこ」になります。「ニシンの子」なのになぜ「かずの子」なのでしょうか?それはニシンがアイヌの名称では「カド」と呼ばれ、「カドの子」が訛って「かずのこ」になったともいわれています。ニシンは北海道では「ハナジロ」「ハナグロ」との別名もあります。


ニシン(鰊)のおいしい食べ方
生ニシンは塩焼きがおススメ
関東や関西地方ではニシンと言えば、身欠きニシンなど干物が一般的なイメージですが、最近は航空便など輸送手段の向上により、それらの地域でも生ニシンを食べることが出来るようになりました。ニシンの魅力は程よい脂の乗りと、柔らかな身肉です。鮮度の良いニシンが手に入ったら、同じ青魚であるイワシなどには無い独特の甘味旨味が食欲をそそりますので、なるべくシンプルで素材そのものを味わうような料理で食べることをおススメします。煮つけ、フライやマリネ等でも美味しい魚ですが、おススメの食べ方は「塩焼き」です。焼くときに少し工夫を。焼く前に塩を振り、浸透圧で魚の臭みを魚の余分な水分とともに出します。出てきた水分をふき取ってから、魚を焼きます。一般的な家庭用グリルで焼くと「上火」で焼くことになりますが、旨味を閉じ込めるため理想は「下火」です。魚を焼くと脂が湧き出ます。その脂が落ち、火に当たることで煙になります。その旨みの煙で燻され、魚がふっくらと膨らむのです。ニシンの地元、北海道では鮮度が良いものは刺身で食べます。身を叩いて「なめろう」で食べることもあるようです。

京都発祥の「にしんそば」は、1882年(明治15)祇園の「松葉」2代目の松野与三吉氏の発案によるもの

京都名物「ニシンとなすと炊いたん」(京都 総本家にしんそば・松葉)。茄子にニシンの旨味がしみ込み、美味しい料理です

福井県若狭地方名物「にしんずし」。ニシンを用いたなれずしです

富山は、北前船により北海道から昆布とともに身欠きニシンが持ち込まれ、「ニシンの昆布巻」が作られた

ニシン(鰊)の豆知識
ニシンと北前船
北海道や日本海側と京都・大阪を結ぶ北前船の物流で、特にニシンと昆布は日本の産業や食文化に大きな影響を与えました。ニシンは室町時代から食用にされていました。大量に獲れたニシンは食用だけではなく、脂を絞り、搾りかすを「ニシン粕」と呼ばれる肥料として北前船で内地へ運んでいました。ニシン油は灯火の燃料になったほか、石鹸やグリセリン、火薬の材料としても利用されました。窒素、リンが豊富で肥料効果が高いニシン粕は、生糸を作るカイコの桑の生育に必要不可欠な肥料でした。(当時、日清、日露戦争にかかる戦費を生糸で稼ぎ出していた)
また瀬戸内の藍や近畿の綿花の生産を一気に拡大させ、関西地方の繊維産業が大きくなり、明治時代の日本の近代化へ大きく寄与しました。北前船の寄港地では、加賀のニシン寿司、京都のニシンそば、大阪のコブ巻などと北の素材をその土地その土地でうまく加工し、それぞれ独自の食文化が発達し郷土を代表する料理となりました。