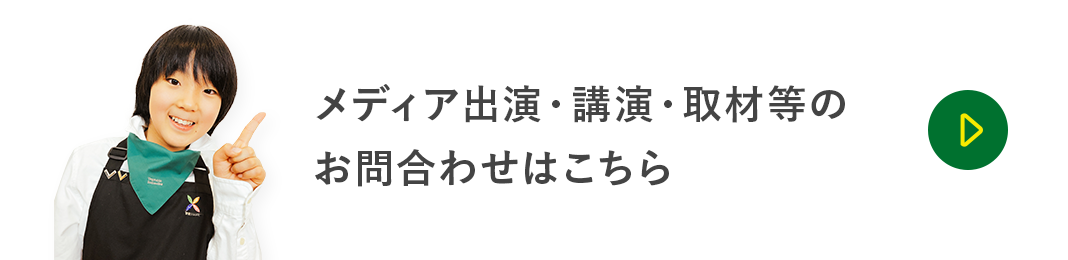【年末年始】 お正月、おせちで食べているものは「筑前煮」、「煮しめ」、「がめ煮」、「うま煮」?
2024.12.31

正月のおせち料理の“定番”に、ニンジン、タケノコなど野菜を煮込んだ、「筑前煮」や「煮しめ」と呼ばれる煮物があります。「筑前煮」と「煮しめ」、見た目はよく似ていますが、同じものなのか、違うものなのか? また、「がめ煮」、「うま煮」はどうなのか、整理しました。
筑前煮
「筑前煮」は福岡県の筑前地方で作られていた郷土料理で、鶏肉や野菜を炒め、甘辛く味付けした煮物です。『鶏肉や野菜を油で炒めてから煮る』、という調理法が筑前地方独特であったために「筑前煮」と呼ばれ、今や日本中で作られる家庭料理になりました。
<調理方法>
「筑前煮」は1つの鍋で食材を炒めてから干しシイタケの戻し汁で煮ます。油で炒めることで食材の表面に膜が出来るので、うま味や水分、栄養が外に出にくくなります。野菜にも油のコクが伝わり、炒めた香ばしさもプラスされるだけでなく、煮崩れしにくくなっています。
煮しめ
野菜・乾物を形を崩さないようゆっくりと時間をかけ、煮汁が残らないように具材に染み込ませることから「煮しめ」と呼ばれます。お重に入れても汁が出ず、冷めてもおいしく食べることができます。煮しめは具材や味付けに決まりがなく(だしが中心の地域、甘辛くする地域も)地域によって根菜類、芋類、コンニャク、油揚げ、昆布、練り物など様々です。
<調理方法>
煮しめは、野菜別にそれぞれ別の鍋で煮て、最後に盛り合わせます。だから、レンコンや里芋は白さが残るくらいに仕上げ、 (全部が茶色に染まってしまわないよう見た目も考えられています。鶏肉が入っていないのは、南北朝から室町時代にかけて、精進料理として食されていたことに由来するようです。具材に味が染み込むのは、煮ている間ではなく、冷めるときに食材に味が染み込みます。具材に火が通ったら火を止め、冷ます工程を入れることで、味の染みた煮しめになります。
がめ煮
がめ煮も筑前煮と同じく、鶏肉と野菜などを油で炒めたのち、砂糖と醤油で甘辛く煮た福岡の代表的な郷土料理です。「がめ煮」という呼び名は博多の方言「がめくりこむ」(寄せ集めるの意味)が由来という説、朝鮮に出兵した兵士が当時「どぶがめ」と呼ばれていたスッポンと、ありあわせの材料を煮込んで食べたのがはじまりという説もあります。一般的に「骨付きの鶏肉」を使うのががめ煮、骨なしの鶏肉を使うのが筑前煮という違いもあります。
うま煮
うま煮は「旨煮」、「甘煮」が由来で、砂糖やしょうゆ、みりんなどで煮たもので、地域によって使われる具材も様々です。九州地方では甘くて濃い味付けですが、関西地方ではだしや薄口しょうゆを使い、あっさりとした味付けが多いです。