福沢諭吉の「肉食のすゝめ」「牛乳のすゝめ」
2025.01.02
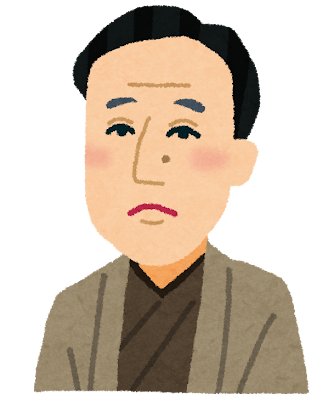
昨年7月、新紙幣が20年ぶりに変わり、新紙幣の肖像に渋沢栄一、津田梅子、北里柴三郎が採用されました。この3人がどういう人なのかは、テレビ番組や雑誌でも取り上げられていましたので、今日は日本資本主義の父と呼ばれる渋沢栄一に代わるまでの40年間、一万円札の肖像だった福沢諭吉についてお話したいと思います。福沢諭吉は慶応義塾大学の創設者で、「天は人の上に人を造らず」などの名言を残したことで有名です。
目次
「肉食のすゝめ」
天武天皇が675年に「殺生肉食禁止の詔」を発令して以来、1200年の長きにわたり牛肉を食べることを禁じられていましたが、1871年(明治4)に肉食の禁が解かれ、翌明治5年に明治天皇は自ら牛肉を試食されています。パンやオムレツ、ステーキなど、洋食が日本人に浸透していくことに大きく貢献したのが福沢諭吉であるといわれています。

洋食も日本人の嗜好に合わせ独自の進化をし、「西洋料理にはない洋食」も誕生しています。
→ クリームシチュー、オムライス、ナポリタン、ドリアなど
「牛乳のすゝめ」
また肉食だけではなく、乳製品の普及にも尽力されたことも有名です。1870年(明治3)、腸チフスを患った福沢諭吉が、その後体力回復に築地牛馬会社の牛乳を取り寄せていました。築地牛馬会社から牛乳の普及をお願いされ、「肉食之説」という宣伝文を書き、牛肉や牛乳が身体のために有効だと強調しました。まだ西洋の食文化になれない人々に牛肉や牛乳を勧めるにあたり、おいしいということだけでなく、栄養面のこともきちんとエビデンスをとって伝えたこと、この点が素晴らしいと思います。平賀源内が「土用丑の日」を広めたことも凄い画期的だったとは思いますが、エビデンスをつけていた福沢諭吉は流石だなぁと思います。
また、味や香りが当時の日本人に合わなかったコーヒーに牛乳を入れミルクコーヒーにすると飲みやすくなると伝えていたことなど、当時の日本にこのようなアイデアを出せる人は、福沢諭吉以外にも存在したのだろうか?と思います。
学問に入らば大いに学問すべし
日本の食文化について調べていくと、いろいろなところに「福沢諭吉」が出てきます。福沢諭吉が「学問のすゝめ」の中で奨励している「学問」は、いわゆる勉強的なものではなく、日常生活や仕事に役立つ実践的な学びである「実学」です。特に第十編にある「学問に入らば大いに学問すべし。農たらば大農となれ、商たらば大商となれ。学者小安に安んずるなかれ。」という部分は、この先の進路の指針になる気がします。




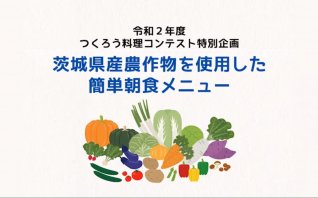

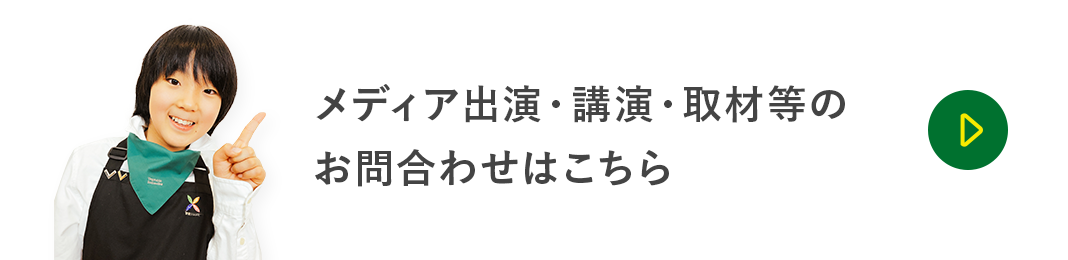
肉は675年の肉食禁止令以降も密かに食べられていたので、庶民を相手とした牛鍋ブームが起こったといわれています